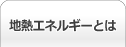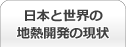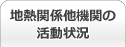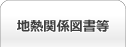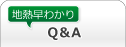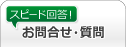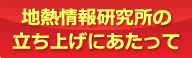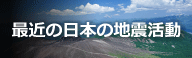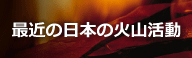毎日新聞2024年9月26日付夕刊は『露大統領 核ドクトリン改定言及 非保有国からの侵略 核兵器で反撃検討』と報じている。
⇒ついにプーチンは、自らが仕掛けた理不尽なウクライナ侵攻がうまくいかず、むしろ逆に敗北しつつあり、当初の目論見を超える、予想外の長期化をし挙句の果てには、一部のロシア領土がウクライナから確保される事態に至り、とんでもないことを考え始めたようだ。
ロシアのプーチン大統領は、「核抑止力の国家政策指針」(核ドクトリン)の改定に言及し、新たな変更案を提示したようだ。
ウクライナは長射程ミサイルを供与している欧米諸国に対し、ロシア領内への攻撃を容認するように求めている。プーチン氏は核使用を示唆することで、欧米にミサイル使用を容認しないように迫った形だ(⇒
変更案では、非核保有国から侵略をうけた場合でも「核保有国の参加や支援があれば共同攻撃」とし、核兵器で反撃することを検討するという(⇒ウクライナでの自らの失敗を棚に上げ隠蔽し、ウクライナを威嚇し、核攻撃を行うことを正当化する、とんでもない独裁者の妄想・妄言だ)。
プーチン氏は、変更案を政府高官が参加する25日の安全保障会議で説明。核兵器をを使用する条件が明確となったとし(自画自賛に過ぎない)、「航空・宇宙兵器が大規模に発射され、国境を越えたという信頼できる情報があった場合」と説明した。また、兵器の例として、戦略航空機、巡航ミサイル、無人機などあげたという(⇒専制君主の驚くべき独善だ。民主国家なら反論が可能だが、ロシアの政府高官にとっては、反論できる余地はない。反論すれば、暗殺されることになるので、誰も反論しない)。
核兵器の標的となる国や軍事同盟が拡大されたとも指摘。同盟国ベラルーシへの侵略があった場合も同様の措置をとるという。プーチン氏は変更案について、「ロシアに対する軍事的脅威とリスクに見合った」ものだと主張(⇒独裁者の独裁的発言と自画自賛)。「重要なのは状況の進展を予測し、(核ドクトリン)現状に適合させることだ」と述べたという(⇒独裁者の自己満足に過ぎない)。
改定時期には触れなかったという。⇒まだ思い付きの段階で、独裁者といえども、まだ自信がないのだろう。現行の核ドクトリンは2020年に策定。核兵器を使用する条件として、ロシア領内対しての、核兵器や大量破壊兵器の使用や、外国からの攻撃で国家が存立の危機に陥るような脅威があった場合などと定めている。
専制国家の独裁者プーチン氏は、ウクライナ侵攻の失敗を国民から非難されることを非常に恐れているようだ。独裁者の自信喪失は危険なシグナルだ。動向を注目しよう。