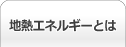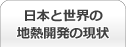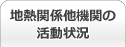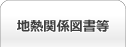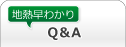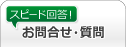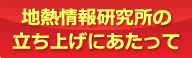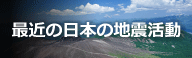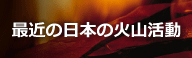毎日新聞2024年11月27日付朝刊一面は『トランプ氏、2カ国(メキシコ、カナダ)に「関税25%」、中国には「10%追加」を明言した』という。トランプ次期米大統領は、メキシコ・カナダ両国に対し、米国に入ってくる不法移民の問題の対抗措置として、全輸入品を対象に一律25%の関税を課す考えを表明したという。政権発足初日の来年1月20日に大統領令に署名し、問題が解決されるまで続ける。中国に対して、違法薬物取引が十分でないことを問題視し、一律10%の追加関税を課すと明言した。トランプ氏は自国産業保護ために、深慮もなく、自国に都合の良い追加課税をするようだ。⇒世界経済は破滅に向かう?
地熱情報研究所
毎日新聞2024年11月26日付朝刊は『温室ガス35年度60%減 政府案COP水準下回る 13年度比』と報じた。次期温室効果ガス排出削減目標について、経済産業、環境両省は25日、2035年度までに13年度比60%減、40年度までに同73%げとする案を公表した。両省の有識者会合で示したという。新たな目標は25年2月までに国連に提出するという。日本は現在、30年度までに13年度比46%減という目標を掲げる。
両省は25日の会合で、1990年度以降で最も排出量が多かった13年度を起点とし、50年度ネットゼロ(排出実質ゼロ)に向けて排出量を直線的に減らしていく場合、経路の中間地点として35年度は60%減、40年度は73%減になると説明。この数値を軸に検討を進めるとした。恐るべき両省のペテンである。こんな論理が国際的に通用するはずがない。驚くべき数値操作だ。これでは何でもできてしまう。両省の官僚は、その程度のまやかしを、学校教育で学んだのか? あるいは、経済産業省・環境省両省入省後学んだのか? 世界の笑いものだ。化石賞を受け、環境政策は世界の最下位グループに入るのも当然だ。
⇒温暖化ガス排出量の世界目標が目標達成年内に実現できないことが現実になることが明確になってしまったので、自分たちでも納得できない「数値操作」をし続けることで、何とか当面だけをしのぐという極低レベルの思考(ウソ)はもうこれ以上すべきではない。世界の恥だ!!!
毎日新聞2024年11月25日付朝刊一面トップはこう報じている。『先進国 資金拠出3倍 温暖化対策 途上国に年46兆円 COP29合意』
アゼルバイジャン・バクーで開催された国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)は24日、途上国で地球温暖化を進めるための資金を巡り、先進国主導の調達目標を2035年までに年3300億ドル(約46兆5000億円)とすることで、合意し、閉幕したという。COP29は「ファイナンス(資金)COP」と呼ばれ、25年以降の資金目標の設定が最大の焦点だった。途上国側からは無償資金で、年1兆3000億ドル(201兆円)に拡大することを目指し、すべての当事者の協力を呼び掛けた。このうち、先進国が主導する分は、25年を期限とする現行目標の年1000億ドルを35年までに年3000億ドルに引き上げる。中国など経済力のある新興国(途上国)を念頭に先進国以外からの自主的な拠出や「南南協力」を促したが、義務化は見送ったという(⇒義務化と言っても中国などは、絶対努力しないだろう。残念ながら)。⇒おそらく、納得した国はごく少ないだろう。しかし、沸騰化した地球は死者が莫大な数に上らない限り、意味のある合意はできないのではないか。残念ながら。人口が今の数分の一以下にならなければ有効な対策は実現できないのではないか。残念ながら、人類の大量滅亡は避けられないのではないか。人類は沸騰化滅亡に向かっており、ごく少数の人類が生き残り、初めからやりなおすしかないのか。もう産業化革命前に戻れないのではないか。そうすると、氷河時代の再来を期待するしかないか。人類はその日がやってくるまで、努力を続けて少数でも残った人類に期待をかけるか。COP29が一応の合意にたどり着けたことは人類は少数になりながらも希望を捨てていないことの証明か。随分情けないことになってしまったが生き残った人類に期待をかけるか。
毎日新聞2024年11月21日付朝刊総合・社会欄は『温暖化対策 日本は最低グループ 独NGOがランキング』と報じた。
日本政府は2050年までにネットゼロ(温室効果ガス排出実質ゼロ)を達成するとしているが、明確なロードマップが示されていないーーー。独NGO「ジャーマンウオッチ」等は20日、各国・地域の気候変動対策を順位付けした報告書「気候変動パフォーマンスインデックス」を公表した。分析対象の64ヶ国・地域中、日本は23年と同じ58位で、5段階評価で最低グループ(53位以下)だった。
報告書は、アゼルバイジャン・バクーで開催中の国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)に合わせて公表された。
ジャーマンウオッチなどは、▽温室効果ガス排出量、▽再生可能エネルギー、▽エネルギー消費、▽気候変動対策 の4分野に関し、これまでの傾向や現状、目標などを分析。世界各国の気候変動対策やエネルギーの専門家約450人がランク付けした。
報告書によると、1~3位は「全ての分野で十分な取り組みをしている国はない」として「該当なし」とした。最高の4位はデンマーク。英国は国内で最後の石炭火力発電所が運転を終了したことなどから,23年の20位から順位を上げ、6位に入った。
⇒なお、デンマークは1970年代のオイルショック時は、日本と同様で、輸入石炭・石油・ガスの使用が中心であったが、その後見事に再生可能エネルギーに転換した結果、このような順位となったが、日本は石油情勢が改善すると、ショックを忘れ、石炭・石油・ガスに逆戻りし、さらに原発を再稼働し、増加させ、また、再生可能エネルギーに力を入れなかった。日本政府はエネルギー転換に完全に失敗した。
日本政府は、デンマークに学ぶべきだ。国の大小は関係ない。政府が意欲をもって、明確な戦略のもと、着実に進展させれば、一国のエネルギー転換は十分可能とする良い例だ。日本政府は、常に「できないづくし」で、転換どころか、逆戻りしてしまった。30~40年でエネルギー転換は十分可能なのだ。近年、世界情勢が不透明な時間が長く続いている。このような時こそ、最低限、エネルギーおよび食糧は、自給を目指して、行動すべきではないか。現在のような、視野が狭くかつ先見性がない政治家では対応は困難だ。国政選挙で、常に議員の入れ替えをしなければならない。選挙に行こう! 国は変えられるのだ。
毎日新聞2024年11月18日付朝刊一面トップは『兵庫知事 斎藤氏再選 不信任受け、出直し選で 稲村氏ら破る』と報じた。
斎藤元彦・前兵庫県知事(47)の失職に伴う知事選が17日投開票され、前職の斎藤氏が、同県元尼崎市長の稲村和美氏(52)ら新人6人を破り再選を果たした。当選の斎藤氏の得票は125,046票、2位の今村氏が117,660票、3位以下は3万票以下で、当選する意欲がなかったか、斎藤氏の得票を減らすための売名行為の立候補だったと思われる。3位の清水貴之氏(27,350票)は、日本維新の会を離党し、立候補したもので、県民は反維新であったようだ。他の落選5氏は結果的に泡まつ候補だったようだ。県民は、知事のハラスメントや議会との対立は、狭い県内でのコップの中の争いとして、争点とはならなかったようだ。多くの県民は、従来から続く県政内部の対立に飽き飽きしており、古い体制にNOを出し、さらに古い体制にしがらみのない若者が多く支持したようだ。これで県内の古い政治体制が破壊され、古くからあった県内の旧態依然たる政治構造は放逐され、兵庫県が新しい政治体制となったということだ。斎藤氏にはハラスメントの問題があることは明らかに感じられたが、県民は、外部の他都道府県民ではよくわからない斎藤前知事の確かな政策立案・実行能力を実際に見聞きして、正しく評価したものだろう。
兵庫県県政の新しいスタートを祝福したい。一方、全国の首長の中には、再選された候補者も少なくない。中には何と6選を受けた人もいる。政治手腕の優れた首長もいると思われるが、中には前任期中に特別の失策がないという、消極的理由で再選された候補も少なくないだろう。自治体住民は候補者の政策立案能力・実行能力を見分ける眼力をつけていけば、国会議員選挙においても、優れた議員が選出され、日本全体が良くなるのではないか。まず国民が自治体選挙において、正しい眼力を養うことが、良い国会議員を選ぶことになるのではないか。今回の兵庫県知事選は良い実例になるのではないか。
なお、上述の意見は、選挙結果が確定していない中で述べたが、選挙確定投票数が本日(11月9日毎日朝刊)掲載されているので、参考までに記録しておきたい。ただし、同日新聞記事にある「ユーチューバー 追い風に」等SNSの発信力強さに関して以外、特に修正することはない。
以下は兵庫県知事選確定得票である。斎藤元彦 当1113911、稲村和 美 976637、清水貴之、258388、大沢義清、73862、立花孝志、19180、 福本繁幸、12721、木島洋嗣、9144 ・・・・・(投票率55.65%)。
毎日新聞2024年11月16日付夕刊はこう報じている。『COP29 日本などG7にNGO「化石賞」COP29』。⇒全くみっともない話だ。日本は毎年受賞し、連続受賞の最低国だ。日本政府は国の代表として、恥ずかしくないのか。石炭火力・原発再稼働で環境最貧国になり下がった。
今回のCOP29は「途上国の地球温暖化対策費支援が最大の焦点だが、支援額の目標案も提出せずに参加し、会議の進展を妨害しいる」と国際NGO「気候行動ネットワーク(CAN)」は断じた。
毎日新聞2024年11月16日付朝刊は『「サヨナラ化石燃料」 日本に抗
議 NGOメンバーら」と報じた。アゼルバイジャン・バクーで開催
中の国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)では、世
界中から集まった若者らが地球温暖化対策強化を求めて会場各所で
デモを続けている。
15日は、日本や韓国、オーストラリアのNGOメンバーら約30人が会場の一角に集まり、各国政府に化石燃料事業への支援をやめるよう訴えた。主催団体によると、化石燃料事業への公的支援の額が大きい日本などへの抗議としてデモを計画。参加者は「サヨナラ化石燃料」などと連呼し、会場を行き交う交渉関係者らにアピールした。
カナダの医療関係者によると、白衣姿で気候変動に伴って深刻化する猛暑や感染症拡大の危機を訴えた。カナダでは2021年の記録的猛暑で600人以上が死亡し、山火事の影響で呼吸器系の症状を訴えて医療機関を受診する人が増加しているという。参加した男性医師は「気候危機は今、健康上の最大の脅威だ。私たち全員の健康と切っても切れない関係にある」と、対策強化を呼び掛けた。
毎日新聞2024年11月15日付朝刊一面トップはこう報じている。
『外資5社42金山跡調査 新鉱脈狙う 環境に懸念』。
外国資本の企業5社が日本国内の計42カ所で金鉱山の開発に向けて
調査や試掘を進めていることが、毎日新聞の取材で判明したとい
う。
いずれも過去に金が採掘されていた場所で、外資は最新技術により
新たな金鉱脈が発見できる可能性があるとしている。
一方で、十分な環境対策や持続的な開発が行われていないことを懸
念する声も上がっているという。
⇒外国企業もいいところに目を付けたようだ。国際市場では金の価
格は上昇する一方で、金鉱山跡であれば、確率は高く、初期投資
も少なくて済む。多くの場合、外国企業は他国の土地であり、意
識が低く、環境問題を考慮しないで開発をする例が実に多いよう
だ。また、ほとんどの場合、持続可能な開発という概念に乏し
い。この問題は、経産省とJOGMECが適切な対応することを期待
したい。
毎日新聞2024年11月8日付朝刊は『福島第1 デブリ回収(わずか数グラム程度) 廃炉最難関 原発事故13年半で初』と報じた。東電は、今後、取りだしスピードを加速度的に上げ、逆算して、40年で完了するとしているが、おそらく不可能だろう。 デブリ総量計880トンとされている。今後も多くの予想できない困難に遭遇するだろう。今後ある時点で40年ですべて回収は困難と国にが判断し、デブリ取り出しは取りやめ,チェルノブイル発電所と同じく、コンクリートで埋設し、石棺方式となる確率が高い。
それまで、東電及び下請け社員は「やってる感」を社会に見せる役割を演じるのだろう。こんな先の見えない仕事に従事する社員はやがていなくなるのではないか。結局、国も東電もだれも責任を取らないのであろう。40年後には現存する関係者はいなくなり、うやむやの中で、廃炉は忘れ去られるのではないか。その時には、政府は原発は必要ないとの判断を下しているのではないか。
毎日新聞2024年11月7日付朝刊一面全面はこう報じている。『米大統領 トランプ氏 ハリス破り返り咲き 最高齢78歳 刑事事件被告』。 「もしトラ」という言葉が交わされていたが、1万分の1くらいの確率(ほとんどあり得ないとの意味)で冗談交じりで語られていたようだが、米国大統領選で実現してしまったのだ。過去に、これほど驚くことはなかった。
⇒風貌・立居振舞・言動・品位・思慮深さ等、どれをとっても、米国大統領として、全くふさわしくない人物が、米大統領選挙で勝ってしまった。こんなことがあるのか。選挙期間中、半ば発狂状態にあるアメリカ社会とはいったいどんなものなのか。
この人物が今後4年間、世界政治で、アメリカ・ファーストを基盤にして、大声を上げ続けるのだ。無視続けることはできるが、それでも地球温暖化問題などには構わず入り込んでくる。バカな言動は無視するしかない。時間の無駄だ。・・・「バカに付ける薬はない」。「バカは死ななきゃ治らない」。
毎日新聞2024年11月6日付夕刊はこう報じている。『北朝鮮兵 多数死亡 米報道 ウクライナと交戦』 ⇒北朝鮮兵は恐らく何も知らされずに、ウクライナの戦場に送られ、苦境のロシア軍の最前線の盾として編入され,露軍の最前線に押し出され、無残にも銃・砲弾の餌食になって死んだようだ。
北朝鮮の金ジョンウンのどす黒い陰謀と侵略者ロシアの苦境を援助するために、無駄死にさせられたようなものだ。似非共産主義国家を守るためのプーチンの苦し紛れの野望の犠牲だ。自国の兵員と武器が不足している落ちぶれたプーチンの軍隊の苦し紛れの狡猾な策だ。プーチンは自国民にはウソで固めた欺瞞が国民に知られ、ついに自滅の道に入ってしまったようだ。
毎日新聞2024年11月6日付夕刊はこう報じている。『富士山うっすら雪化粧』。⇒関東地方に木枯らし1号が吹くかもしれないという情報もある。折から季節は「立冬入り」直後。これから本格的な冬到来となるか。札幌でも積雪になりそうである。
毎日新聞2024年11月5日付朝刊2面(総合)は、”気候革命COP29”と銘打って、COP29が、来週の11月11日からアゼルバイジャンの首都バクーで開幕するのに合わせて、世界及び日本のCOP29準備状況を、やや否定的に、紹介している。
見出しは『資金調達 最大の焦点 先進国の歩み寄り不可欠 気温上昇阻止 見通せず』となっている。
数百兆円をどうかき集めるかーー。11日にアゼルバイジャンの首都バクー)で開幕する国連気候変動枠組み条約国会議(COP29)は、途上国の地球温暖化対策のための資金調達が最大の焦点で、「ファイナンス(資金)COP29」とも呼ばれるという。先進国の歩み寄りが欠かせず、米大統領選の結果も交渉ムードに影響しそうだという。合意の行方は見通せない」というのが、実情のようだ。
「意見の相違は脇に置き、非難し合うのはやめて共通点を見つけていくべきだ」。10月にバクーで開かれた閣僚級に事前会合で、アゼルバイジャンのアリエフ大統領は出席者に呼び掛けた。
COP29での政府間交渉の争点の一つが2025年以降に世界が拠出する途上国向けの資金の規模だ。ドナー(出し手)の範囲も大きなポイントになるという。
COP29での交渉は難航必至だが、気温上昇を1.5℃にとどめるために残された時間はもうほとんどない。
最後に日本に課せられた問題を改めて示し、終わることにしよう。日本の現行目標は「30年度までに13年度比46%減」、先進国は「35年までに19年比60%減」以上の削減が期待されているが、19年度比に換算すると「37%減」。先進国は『35年までに60%』i以上の削減が期待されているが,19年度比に換算すると「37%減」にとどまり、新目標は当然大幅な上積みが求められる。ただし、22年度の排出量13年度比、19.3%減で、30年度目標すら達成が危ういのが現状だ。現在の政府(経産省)の議論では、画期的な進展は期待できない。COP29には一体何を持っていくのだろうか? 具体的な数値は上げられず、お茶を濁して、世界からは総スカンを食うのではないか。最悪の事態だ。
毎日新聞2024年11月4日付朝刊埼玉県版は『埼玉医大 ニューイヤーへ 東日本実業団駅伝 10位滑り込み』と報じた。
活動資金が潤沢で、練習環境が良い大企業の実業団チームに比べて、恵まれているとは言えない地方大学チームが、ニューイヤー駅伝の切符を強豪ぞろいの中で、埼玉医大は見事に獲得した(10位以内)。
地元という意味だけではなく、がん治療をしていただいたという意味からも、埼玉医大の駅伝チームを応援したい。がんばれ!
毎日新聞2024年11月4日付朝刊一面トップは『微粒子で「地球を冷やす」 米ベンチャー・環境ビジネス参入 効果不明瞭 科学者批判』と報じた。
⇒科学に無知な、物事の一面しか見ない、ビジネスマンの独りよがりなインチキ人間からのようだ。アメリカ人はトランプのように物事の一面だけしか見られない、カネの亡者が多いということか。既に投資を呼び掛けており、日本在住者で複数購入者がすでにいるらしい。どの程度投資したかはわからないが、科学の基礎を勉強してから投資すべきだろう。
毎日新聞2024年11月2日朝刊一面で『3党枠組み大筋合意 国民と自公
立憲「閣外協力だ」自立・自国党首 11日会談で調整 公明代表に斎藤氏調整』と報じている。「宙づり国会」も各党組み合わせの枠組みも固まってきたようだ。立憲は最大野党なのに、仲間に入れず。何度も書くが、選挙前および選挙中に、野党共闘のための声掛けをせず、孤立選挙になったことが大きく響いている。国民は、公明党を抜いて多数党になったことが、自民から声がかかったようだ。議員数は圧倒的に少ないので、自己の政策がどれだけ採用されるか。かなり頑張らないと自民党に騙されかねない。公明党は委員長が落選し、議員数も大幅に減った。斎藤氏が代表になっても、リーダーとして不適当と思われるので、今後沈んでいくのではないか。維新は大阪だけでかつ唯我独尊なので、このままでは国政における発言力は低下するだろう。共産党も党風を変えない限り、沈没に向かうのではないか。
毎日新聞2024年11月1日付朝刊一面は『不登校小中生最多34万人 文科省調査 専門家の支援不足』と報じている。
⇒想像を超える多数だ。文科省は、専門家の支援不足と言っているようだが、そんな一言で済ませられるのか。深く検討すれば、小中学校(義務教育)制度を根本的に見つめ直すきっかけとなるのではないか。
毎日新聞2024年11月1日付朝刊は『エネルギー計画 年内にも改定案 首相』
⇒政府は2035年以降の温室効果ガス排出削減の新たな目標を盛り込んだ「地球温暖化対策計画」を年内にも素案を示すという。千枚舌の石破首相のことだ。迷案を提案して、またぞろ、直後に修整するのではないか。
これまで日本政府はエネルギー計画や脱炭素計画は、のらりくらりで、国の内外から総スカンを食らい続けてきたので、どれほど画期的な計画が出てきても、驚かない。しかし、今度は、政府が自信をもって練り上げたものが国の内外から総スカンを食わないことを密かに祈りたい。
しかしながら、エネルギー基本政策を検討する委員会から漏れてくる、これまでの議論の流れからすれば、評価は国の内外から非難轟々の酷いものにならざるを得ないのではないか。それとも、形だけは取り繕うか。いずれにしても、日本政府は新しい「脱炭素計画」で世界の主流にはなれないだろう。むしろ反発を受けるだけだろう。嘆かわしいことだ。
毎日新聞2024年10月31日付朝刊は『車世界生産6%減 今年度上半期 国内大手8社』と報じた。国内自動車大手8社が30日発表した2024年度上半期(4~9月)の世界生産台数は、前年同期比6.0%減の1187万8301台だった。
認証不正問題による生産停止や、中国市場で苦戦が響いたという。共同通信の集計によると、上半期として前年実績を下回るのは新型コロナウィルス禍が打撃となった20年度以来4年ぶり。中国での競争激化に加え、重要市場の米国も11月5日の大統領選の結果次第で関税引き上げなど日本メーカーに不利な政策変更が実施される恐れがあり、世界生産の先行きは予断を許さない状況という。世界生産は、スズキとマツダを除く6社がマイナスだった。最大手のトヨタ自動車は7.6%減の430万5037台に落ち込んだ。ホンダが8.1%減の181万7415台、日産自動車が7.0%減の153万2501台となった。
中国では、トヨタやホンダ、日産がいずれも現地の電気自動車(EV)メーカーなどとの価格競争を強いられ、生産台数を減らしたトヨタは国内では認証不正に伴うスポーツタイプ多目的車(SUV)「ヤリスクロス」などの生産停止が響いた。
毎日新聞2024年10月31日付朝刊一面は『「同性婚認めず」は「違憲」東京高裁判決 控訴審で2例目』と報じた。
⇒遅きに失したが、全く当然な判決である。世界の動向に比べ、一周以上遅れたが、世界に民主国家入りを果たせそうだ。
最高裁は世界の動向をしっかりと受け止めてほしい。
毎日新聞2024年10月31日付朝刊一面トップは『宙づり国会 自公と国民 政策協議に 維新、協力に消極的 立憲の多数派工作 難航 世耕氏ら6人が自民会派入り』と報じた。⇒立憲は議員数は大幅に増えたが、選挙前の協力姿勢が不十分で、多数派工作は失敗のようだ。自ら身を切る態度を示さない限り、多数派工作はうまく行くはずがない。すべて、選挙前、選挙中の行動が消極的過ぎた。
したがって、現在の時点では自公に、国民が課題による部分連合となりそうである。当然だが、国民は自公と連立する意思は全くないようだ。今後、政策の実行までは時間がかかりそうだが、日本国民が民主政治の学校に入って学ぶ時間と考えればよいのではないか。
政治は一瞬先は見えないと言われるが、今後ウルトラCが出ないとも限らない。場合によっては、国会議事堂前で、意思表示をするような機会があるかもしれない。今回を逃すと日本の政治改革は数10年後以降になってしまうかもしれない。
毎日新聞2024年10月30日付朝刊一面は『生活苦で自殺 2年で1.5倍 昨年、物価高背景か』と報じている。
政府は29日、2024年版の自殺対策白書を閣議決定した。23年の自殺者数は2万1837人で、前年(2万1881人)をわずかに下回った。自殺の原因・動機(複数計上可)別では「経済・生活問題」が前年比484人増の5181人で、この2年で1.5倍に増加した。厚生労働省は21年の後半から始まった物価高による生活苦が背景にあるとみている。男女別では男性は1万4862人(前年比116人増)と2年連続で増加、女性は6975人(同160人減)で4年ぶりに減少した。小中高性は513人(同1人減)で過去最多であった前年と同水準であったという。⇒自殺は痛ましいが、特に小中高生の自殺が年間500人位もいるのは、前途有為な若者だけに、特に痛ましい。
毎日新聞2024年10月30日付朝刊一面は『女川2号機再稼働 福島第1と同型 被災原発で初 東北電力』と報じた。東北電力は目の前の状況だけを考えて、世界の動向に反する決定をしたようだ。これからも福島第1原発事故と同じ事故発生を案じながら運転することになる。
大手電力会社は何故原発、石炭火力発電から再生可能エネルギー発電に展開できないのか。日本の電力政策は国および大手電力会社ともに、世界から何と言われようとも、原発・石炭火力発電を続けるようだ。このまま世界の笑いものになり続けることを後ろめたく感じないのか。地球が「温暖化から沸騰化」に移行しつつある中で、世界人類の将来を見据えた決断が何故できないのか。不可思議である。
毎日新聞2024年10月30日付朝刊一面トップは『宙づり国会 政権命運握る国民民主 鍵はトリガー条項』と報じている。27日投開票の衆院選で自民、公明両党の獲得議席が過半数を割り込み、衆院に過半数を占める勢力がいなくなる「ハングパーラメント(宙づり国会)」が出現したことを受け、与野党は29日、政権枠組みの駆け引きを本格化させたという。キャスチングボートを握る国民民主党の玉木雄一郎代表は、「少数与党」での石破政権継続を容認し、政策ごとに連携する「部分連合」に前向きな姿勢を示した。⇒当面、賢明な選択だろう。
⇒国民民主党は公明党より衆院議員が多く、与党内の発言は、公明党より重要な位置を占めることになり、自党の考えが政権の考えになる可能性が高く、強い発言力を持つことになった。今後の参院選挙、衆院選挙で勢力を増していくだろう。
これに対し、立憲民主党は国民民主党に比べはるかに多い衆院議員数を獲得したにもかかわらず、政権を担う政党として、全く名前が上がってこない。これは、野田代表の選挙前、選挙中の政権構想打ち出しの戦略の失敗と思われる。野田代表は、安倍政権にも石破政権にも騙され、苦渋を飲まされている。経験を活かしていない。野田氏の個人的な戦略失敗にあるのではないか。立憲民主党は、今後の参院選挙、衆院選挙を勝ち抜き、政権奪取するためには、トップを変える必要があるのではないか。
毎日新聞2014年10月28日付朝刊一面トップは『自公過半数割れ 立憲、国民が躍進 「政治とカネ」響く 首相 政権継続意欲』と報じた。⇒首相は大多数の国民の信頼を失ったのだから辞任すべきではないのか。「政権継続意欲」とは滑稽である。今後の国会でのスケジュールを明確に示した後に、辞職を表明すべきだ。なお、国会を解散するような愚行は許されない。国会で十分審議し、政治の改革の道筋を国民に明示してから、責任を明らかにし、辞職して、新首相を選出すべきだ。
大方の予想を裏切る(事前のメディア予想はほとんど当たってない。毎日新聞も同様である。数日前、「自公」でどうやら過半数という)甘々の予想であった。本欄ではそれに同意できないことをコメントしたが、その通りになった。全国で数100人(または?)1000人以上の記者が現地情報を入手し、分析し、本社の編集委員会でも十分議論して、結論を出したと思われるが、この見通しの過ちは、全国レベルの新聞の能力と意欲の弱体化を如実に示しているのではないか。社説では十分な反省の弁が聞きたい。毎日新聞社は予測の失敗について、社説で十分な反省を述べてほしい。
毎日新聞2024年10月26日付朝刊一面トップは『裏金問題 明日審判 衆院選投開票 過半数巡り激戦』と報じた。裏金選挙区に自民党は意味不明の2000万円を支給したようだが、これが輪をかけた愚策・失策となり、激戦区では軒並み議席を失うようだという。国民をだまし、甘く見ている自民党は、選挙戦の最後で大失敗をしたようだ。⇒明日の午後8時が待たれる。
Institute for Geothermal Information. All Rights Reserved.